「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」新薬5剤を含む治療アルゴリズムの考え方は
自分用のメモです。以下は、記事の抜粋です。
新規薬剤の発売が相次ぐアトピー性皮膚炎について、2024年10月に3年ぶりの改訂版となる「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」が発表された。外用薬のホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害薬ジファミラスト、注射薬の抗IL-31受容体A抗体ネモリズマブおよび抗IL-13受容体抗体トラロキヌマブ、経口JAK阻害薬ウパダシチニブおよびアブロシチニブの5剤が、今版で新たに掲載されている。常深 祐一郎氏(埼玉医大)に、新薬5剤を含めた治療アルゴリズムの考え方について話を聞いた。
寛解導入のメインはまず“ステロイドの適切な使用”で変わりない
ジファミラストを含む非ステロイド系外用薬の選択肢が増えている。寛解導入での位置付けについて常深氏は「軽い皮疹の場合に非ステロイド系で寛解導入もありうるが、メインはやはりステロイド系外用薬」と話し、ランクの選択を含めてステロイドをどう適切に使えるかが非常に重要とした。落ち着いたらランクを下げるもしくは非ステロイド系に切り替えるといった使い方が望ましいと話した。
一方、ステロイド系外用薬は局所的な副作用が出るなど長期使用には向かないため、寛解維持の外用療法のメインとしては非ステロイド系外用薬が適している。「患者さんごとに使ってみて使いやすいものを選ぶといった考え方もよいのではないか」と柔軟な対応を提案した。
全身療法の使いどころ、使い分けは?
全身療法は中等症以上の多くのアトピー性皮膚炎患者に対して推奨されている。「必ずしも外用療法をやりきってから全身療法という考え方ではなく、患者さんが外用療法に疲れてしまったり時間をかけてQOLが下がってしまったりという状況になる前に、使用ガイダンスで示された条件を満たしたうえで早めに全身療法に切り替えるのも1つの選択肢」と私見を交えて解説した。
注射薬である抗体製剤(デュピルマブ、トラロキヌマブ、レブリキズマブ)の特徴として、常深氏は、投与前後の検査不要で安全性が高いこと、幅広い患者に有効性があることを挙げた。それに対して経口JAK阻害薬(バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブ)は、投与後も画像を含めた検査が必要であり、効き始めは早いがレスポンダーとノンレスポンダーが分かれる傾向があるという。「経口がやはり楽という患者さんもいるし、数週間おきの注射のほうがむしろ楽という患者さんもいる」とし、上記の特徴も踏まえた選択が重要と話した。
抗体製剤やJAK阻害薬には治療費の問題がある。同氏は治療費がハードルになるケースでは、従来からの全身療法薬であるシクロスポリンをしっかりと使っていくことも大事と指摘。「悪くなりかけた際にシクロスポリンを使うという使い方で、短期の使用であれば副作用の可能性も低い」とした。
アトピーはいまや“すごくよくなる”疾患、患者も医療者もイメージを変えていく必要
アトピー性皮膚炎には以前から“なかなか治らない疾患”というイメージが根強くあり、そもそも医療機関にかかっていない患者も多い。しかし有効な薬剤が複数登場し、適切な治療により、アルゴリズムで治療のゴールとして示された「症状がないか、あっても軽微で、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない」状況を実現することができるようになっている。
常深氏は、医師を含む医療者が“アトピーは外用薬しかない”、あるいは“改善の難しい疾患だからあまりよくならなくても仕方がない”と思っていたらそこで治療は止まってしまうとし、「抗体製剤使用のハードルは決して高くなく、要件を満たせばクリニックでも使用できる。また自院で使用しなくても、必要性を感じた場合は専門医に積極的につないでほしい」と話した。
「アトピー性皮膚炎には以前から“なかなか治らない疾患”というイメージが根強くあり、そもそも医療機関にかかっていない患者も多い。」という現状は強く実感しています。また、残念ながら同様のイメージを持つ医師も多いです。“すごくよくなる”病気であることを広めたいと思います。


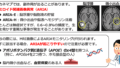
コメント