“小太り”でも他の疾病の合併あれば肥満症治療の対象に
以下は、記事の抜粋です。
GLP-1受容体作動薬のセマグルチド(ウゴービ®)ならびにGIP/GLP-1受容体作動薬のチルゼパチド(ゼップバウンド®)の登場により、肥満症治療のすそ野が大きく広がりつつある。
これらの薬剤は処方前に、6カ月以上の食事・運動療法を行うことなどが定められているほか、処方できる医療機関の要件が厚生労働省の「最適使用推進ガイドライン」に盛り込まれ、処方に制約が設けられている。
だが、神戸大学の小川渉氏はこう評価する。「高い減量効果が期待できる両薬剤の登場は、肥満症の治療選択を大きく変えた。中でもゼップバウンドは臨床試験において、72週で約20%の体重減少率を達成した。処方数は増えるのではないかと予想している」。
セマグルチドとチルゼパチドは2型糖尿病の治療薬として用いられてきた薬剤であり、使用実績が豊富だ。さらには適応に、「2型糖尿病、脂質異常症、高血圧のいずれか1つを合併するBMI 35kg/m2以上の肥満症」に加えて「BMIが27kg/m2以上で2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する肥満症」も含まれている。
「肥満症の概念や診断基準はあまり臨床現場に浸透していないように感じている。“小太り”で、なおかつ生活習慣病などの健康障害を抱えている患者は、肥満症治療の対象になる。だが現状では、高度肥満症に該当しなければ治療介入の必要がないと考える医師も多いようだ。また肥満症治療によって改善する健康障害は、いわゆる生活習慣病以外にも、変形性関節症などの運動器疾患、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患、月経周期異常や不妊などの婦人科疾患と幅広い。様々な健康障害を合併した肥満症患者に、より積極的な介入を検討してほしい」と小川氏は語る。
セマグルチドとチルゼパチドにおける最適使用推進ガイドラインで規定されている処方対象は、以下の通り。(1)高血圧、脂質異常症、2型糖尿病、肥満症に関する最新の診療ガイドラインを参考に、適切な食事療法・運動療法に係る治療計画の作成、(2)計画に基づく治療を6カ月以上実施、(3)その間に2カ月に1回以上の頻度で管理栄養士による栄養指導を行い、(4)患者自身による記録を確認するなど必要な対応を実施──以上の治療・指導を行っても、十分な減量効果が得られない患者。
太字の部分のように適応を広げると肥満治療の医療費は増えますが、その分高血圧、脂質異常症、2型糖尿病は減ることが予想されるので、これらに使われていた医療費は減るかもしれません。今後の展開を注目したいと思います。
ちなみに、BMIが27というのは、身長160cmなら体重は約69kg、170㎝なら約78kgです。BMI(Body Mass Index)は、体重(kg)を身長(m)の2乗で割った値で、肥満度を表す指標です(BMI計算サイトへ)。


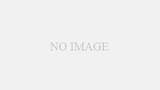
コメント